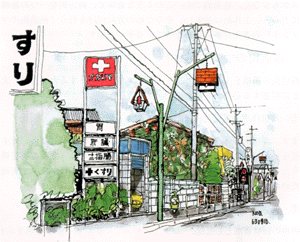商店街活性化のためのマネジメント
|
|
平成11年度 全振連で行った商店街近代化研究会報告書を要約したものです。
(商店街近代化推進シリーズ45)
|
| |
| 1.商店街マネジメント |
| (1)商店街マネジメントの必要性 |
自然発生的にできた商店街が大半ですが、商店街組織の存続、発展のために、個店が協力して1つの組織として活動しなければなりません。また、商店街が環境の変化に対処するためには、自らの経営目標を明確に持っていなければなりません。そしてこの経営目標の観点から環境変化に立ち向かい、環境変化の中で経営目標を実現する機会を発見し、それを実行に移すのです。
一方、今日の環境変動は、かつての高度経済成長の社会で育まれてきた理念、考え方、方法、経験を革新していくことを要請しています。そこで、商店街自体の意識革命が必要で、新しい社会や環境への正しい洞察と新しい展望、新しい理念と新しい方向づけが不可欠となっています。それには個別での対応よりも組織体として商店街全体で適応、対応していくほうがリスクも少なく、効果的です。このような意味で、商店街を一つの組織としてとらえ、主体的に対応し、そのための方向づけを行う"商店街のマネジメント"の考え方が必要になっているといえます。
|
| |
| (2)商店街のマネジメント |
| 商店街の組織を1つのまとまりとしてマネジメントするためには、次のことに留意する必要があります。 |
| |
① 経営理念の明確化 |
まず、商店街の「経営理念を明確にする」ことです。地域社会に対する責任をいかに果たすのか、そこに暮らす消費者にどのような便益を提供しようと考えるのかを外部に表明し、商店街内部に対しては、それを実現するための具体的な策を提示する必要があります。
|
| ② 経営資源の活用 |
組織の経営資源としては、"ヒド"、"モノ"、"カネ''、"情報"が考えられ、商店街においても同様に資源を有しており、「経営資源を有効活用する」ことを考えなければなりません。このうち、商店街組織を動かすのが"ヒト"であることから、人材不足は商店街の問題といえます。リーダーや役員の高齢化に伴い、後継者の育成に配慮しなければなりません。
|
| ③ 責任と権限の一体性の確認 |
|
人材と関連するのが、組織において「責任と権限の一体性を確認する」ことです。"責任"とは、職務上の義務を意味し、この義務や責任は、反面、職務を遂行する"権限"を伴うものでなければなりません。例えば、商店街の若手に責任だけ委譲して、決定する権限を委譲しないことは、人の育成の障害となり、大きな問題です。責任と義務の一体性を確認した上で、分散型の分権的組織も、商店街において有効になります。
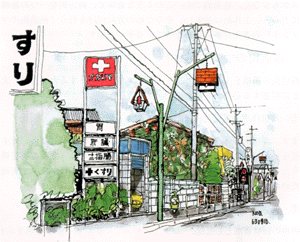
|
| |
| 2.商店街マネジメントの困難性 |
| (1)商店街組織の特異性とマネジメントの限界 |
| 商店街は、統一された目的で組織化がなされた訳ではなく、個々の店の加入した動機や目的は、"事業"、"親睦"、"付き合い"などまちまちです。
したがって、商店街組織は、一般の企業組織と比べて特異であることになります。そのため、通常の組織とは異なり、マネジメントの限界が認められます。 |
| |
① 非営利的イメージの強い商店街組織 |
商店街組織は、構成員個々で共通認識できる最大公約数的利害を目的として組織化されるのが通常で、原則として活動に営利を追求する組織ではありません。
|
| ② 共通理念の不足 |
商店街は異業種集団であり、それぞれの企業が個別に経営目的を持っているため、組織としての共通理念が存在しません。
|
| ③ 組織帰属意識の欠如 |
多くの構成員では、商店街組織に対する帰属意識、創業者意識はほとんどないと考えられます。
|
| ④ リーダーの不在 |
創業者的意識をもった強烈なリーダーが存在し、次期後継者を育成し事業継承している例は非常にまれです。
|
| ⑤ ゆるい結束組織 |
それぞれの商店が固有の事業意識を持っているため、意識の統一も図りにくく、共通の行動原則作りも難しくなっています。
|
| ⑥ 事業目的型組織になりやすい |
各事業に相互関連性が薄く、商店街が実施する事業は単独個別に実施されています。
|
| ⑦ 商店街事務局の不在 |
商店街活動の中枢機関に事務局がないことが、事業の進捗や正確さにもっとも大きな影響を与えています。
|
| ⑧ 増加する商店街内チェーン店 |
チェーン店本部は商店街の外部に立地する場合がほとんどで、チェーン個店の段階では共同意識を持った活動がしにくいのが実情です。
|
| |
| (2)商店街が克服すべきマネジメント上の課題 |
商店街の活動を円滑に進める上で、マネジメントの限界や困難性がいくつか存在しています。これらを克服する上での主な課題は次の5点です。
|
| |
① マネジメント組織の強固化 |
|
組織の中で役割分担が明確に行われ、マネジメントのどの分野にも力を集中しやすい態勢をとることが、これからの商店街が始めなければならないことです。
|
| ② 収益の安定 |
事業を継続的に実施してゆくため資金の安定性があるかどうかは大きな成果の分かれ道です。
|
| ③ 意識の統一 |
種々の事業を実施していくためには、経営規模、経営形態、業種業態などが異なる組合員の意識、意思の統一を図ることが第一です。
|
| ④ 事務局の設置 |
決定事項をとりまとめ、行政の窓口となり、組合員の代理業務を実施し、統合していく事務局は、商店街のマネジメントを実施する上で、非常に重要です。
|
| ⑤ 運営目的の統一 |
|
商店街の運営目的を明確にして、行動や意識を事業ごとに個別に統一して事業を展開していくことが大切です。

|
| |
| 3.商店街マネジメントの組織 |
| (1)商店街マネジメントの実態 |
| 各地の商店街で行われている商店街のマネジメントの実態として、次の事項が指摘できます。 |
| |
① 実践力に優れた指導者による全体管理体制 |
活発に活動している商店街は例外なく、意欲的で実践力に富んだ指導者に恵まれ、この指導者を中心として、全体管理体制をとっています。
|
| ② 賦課金の徴収 |
賦課金を徴収しているものの、その絶対額が少なく、活発で先進的な資金活動とはなりにくいのが実態です。
|
| ③ 環境整備事業と共同経済事業の実施 |
販売促進他のソフト事業(共同経済事業)は多くの商店街が実施しており、環境整備事業はやや実施率が低下します。
|
| ④ 研修事業 |
経営環境が変化すれば当然経営体質も変化しなくてはならず、このことを最も効果的に実施する内部活動が研修事業です。
|
| |
| (2)事業推進事務局からマネジメント組織ヘ |
マンネリ化した均質的な事業を廃し、経営環境を把握した戦略的マネジメントの実践が必要です。そのためには、商店街の事務局においても、事業推進事務局から環境変化に迅速に戦略的に対応できるマネジメント推進組織へと変化していかなければなりません。
|
| |
| (3)マネジメント人材の必要性 |
マネジメントの実践は人によって実現する要素が多いため、組織内にマネジメントに長けた人材が必要です。偏りのない科学性、柔軟性、普遍性を重視した活力ある人材の発掘と育成が必要です。
|
| |
| (4)あるべき商店街のマネジメント |
| |
① マーケティング・マネジメントヘの期待 |
厳しい環境変化の中で、商店街が成長し、発展してゆくためには、これまでのようなハード事業やソフト事業の積極的な実施に加え、「消費者」といったような巨視的(マクロ的)な環境変化でなく、より「個人」的なミクロの市場の変化に的確に対応したマネジメント力が必要です。
|
| ② 商店街のマーチャンダイジング(MD)の必要性 |
|
消費者及び競合対策上最も重要な要因はMD対策です。MDは主として商店での商品政策をさしていますが、商店街のMDは商店街を構成する業種構成で、その取扱商品の特性や水準、嗜好に関わるものです。

|